| 編集 雑記帳 |
| ■ 編集の基礎 | |
|
今日は本の編集をするときに知っておくと良い基礎的なことがらを扱ってみます。 本を作っていくとき 1.本の各部の名称 2.原稿 ・ 版下の各部の名称 3.本のとじの各種の名称 について、正しい呼び方を知っていると便利です。 | |
| 1. |
まず、図1、2 で、本の各部の名称を示しました。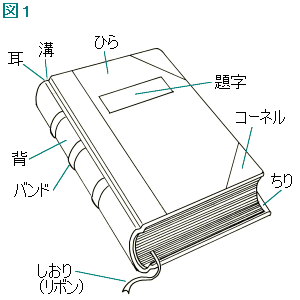 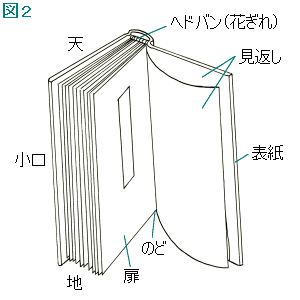 「見返し」 「扉」 「のど」 「小口」 などはよく使います。 また特別なページの作り方として、図3のような 「観音開き」 「片観音」 などの作り方があります。 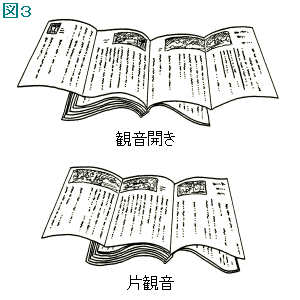 |
| 2. |
次に、図4で、原稿や版下の各部の名称を示しました。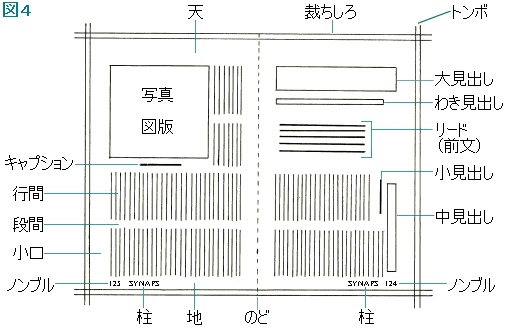 1ページの中で、 「版面」 (はんづら、印刷される版の面積のこと、ふつう 柱、ノンブル は別に考える)の位置や大きさがどうなっているかが重要です。 場合によっては、写真などを版面からはみ出させたり 「裁ち落とし」 にしたりすることもあります。 尚、 「柱」 は、内容を識別する便のために、版面の上部または下部に印刷された書名・章節のタイトルのことですが、元は小口側に柱のように縦組みでつけたことから、この名があるようです。 また、図には示しませんでしたが、 「注」 の入れ方にもいろいろあります。 1.割注(わりちゅう)・・・その語のすぐあとに2行くらいにわたって入れる注 2.傍注(ぼうちゅう)・・・本文の行間に入れる注 3.頭注(とうちゅう)・・・縦組みなどで、組版の上部に入れる注 4.側注(そくちゅう)・・・横組みなどで、組版の右(左)部に入れる注 5.脚注(きゃくちゅう)・・・組版の下部に入れる注 6.補注(ほちゅう)・・・章末または本文の終わりにまとめて入れる注 |
| 3. |
次に、図5で、本の 「とじ」 の名称を示しました。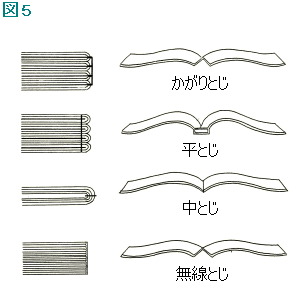 「かがりとじ」 は本製本で用い、木綿糸で折り丁を1つずつとじたものです。 「平とじ」 「中とじ」 は 「針金とじ」 で、いずれもホチキスでとじたものです。 「平とじ」 は教科書や雑誌で用いられ、製本費としては安価ですが、開き具合があまりよくありません。 「中とじ」 は週刊誌やパンフレットなどで用いられます。いっぱいに開けますが、背文字は入れられません。 「無線とじ」 は接着剤でとじるもので、折りの背にぎざぎざを入れて接着剤がつきやすくしたものを 「網代(あじろ)」 といい、よく用いられています。 |
HOME - What's New - 編集 - 会社概要 - 開発 - 人材募集 - Information